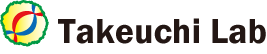集中講義「エントロピー概論」のお知らせ(11/23-25、佐々真一教授)
講師
佐々真一教授(京都大学)
集中講義日時
11/23(水・祝):14:00-15:30, 15:45-17:15
11/24(木) :10:45-12:15, 14:00-15:30
11/25(金) :10:45-12:15, 14:00-15:30, 15:45-17:15
※関連セミナーを 11/24(木) 16:00-17:00 に開催
レポートについて
講義中に出題されたレポート問題を2問以上解くこと。
提出期限:12月16日(金) 締切厳守
提出先:物理本館2階事務(本館298B室)
場所
東京工業大学 大岡山キャンパス 西5号館2階 W521講義室
西5号館は本館横にあります。こちらの地図の13番を目指してお出で下さい。
13番と14番の間の通路から西5号館に行けます。
W521室は2階ですが、建物入口は3階なので、階段を降りてください。
(セミナー開催場所は検討中 - 本館2階284AB室か西5号館2階W521講義室のどちらかです)
講義概要とねらい
エントロピーは乱雑さを特徴づける量である。基礎物理学の重要な概念であるだけでなく、様々な自然科学の分野にも発展してきた。さらに、近年では、異なる形のエントロピー同士のより深い関係が明らかにされ、それを通して自然法則の豊かな見方が提示された。本講義では、学部生向けの物理の講義では触れられることがない、様々なエントロピーを紹介する。具体的には、操作限界を定式化したLieb-Yngvason理論の初等的導入、熱力学変数のゆらぎを熱力学と結びつけるEinsteinの理論の現代的解説、情報の操作限界を定式化するShannonの理論入門、カオス(ランダムネス)の基礎となるBrudnoの定理への入門、最近の研究結果であるネーター不変量としてのエントロピーの説明(セミナー)、そして、非平衡におけるエントロピーの役割に関する議論などを予定している。全体として有機的になっているわけではなく、各々のエントロピー相互の関係について詳細に議論する余裕はないが、それらについても簡単に議論したい。
到達目標
それぞれの項目におけるエントロピーの定義、その背景、そして、使われ方を理解する。それらを通して、エントロピーを深く理解するとともに、関連する学問体系にも入門する。
授業計画
佐々教授による講義ページも参照
11/23 (水・祝)
1章 導入 (20 分)
1.1 講義の目的
1.2 講義の構成
2章 熱力学再訪 (60分)
2.1 熱力学とは
2.2 不変量としてのエントロピーの特徴づけ:例
2.3 Lieb-Yngavason 熱力学
3章 統計力学再訪 (1コマ)
3.1 断熱定理(例:調和振動子)
3.2 エルゴード断熱定理(1960)の紹介
3.3”物理的” 断熱定理(1910)と統計力学
11/24 (木)
4章 情報理論入門 (2コマ)
4.1 「情報獲得」(=不確かさの減少)の特徴づけ
4.2 本質的一意性
4.2 符号化を介した「不確かさ」の普遍的定量化
セミナー:
ネーター不変量としての熱力学エントロピー
11/25 (金)
5章 複雑性理論超入門 (1コマ)
5.1 複雑性の定義とランダムネス
5.2 「確率」からみたランダムネス
5.3 複雑性と不確かさとの定量的関係
6章 熱力学第2法則 (2コマ)
6.1 Jarzynski経由によるquick derivation
6.2 その問題点
6.3 情報理論的定式化
6.4 マクロな時間発展の安定性と熱力学第2法則
6.5 平衡状態の特徴づけ (orthodics)
6.6 エントロピー間の関係
7章 その他 (もし、時間があれば..)
7.1 時系列に対するエントロピー
7.2 非平衡定常状態に対するエントロピー
7.3 エントロピーの統一理論に向けて
シラバス上の講義名称
修士課程:物理学特別講義第五 PHY.P534
博士課程:物理学特別講義発展第五 PHY.P634
(理学院物理学系物理学コース)
問い合わせ先
竹内一将
kat@kaztake.org